
雪国を旅する、とっておきの時間
宿から体験までご要望に応じて、あなただけの滞在プランを手配させていただきます。
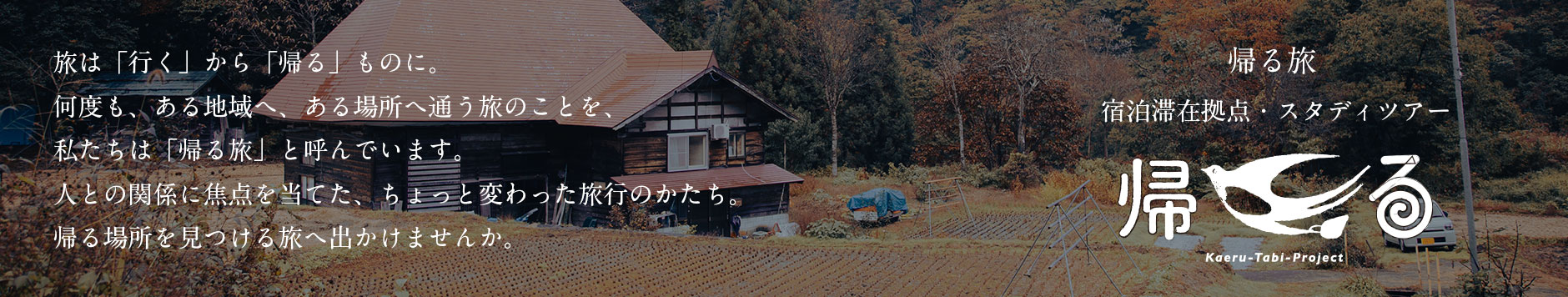



雪国文化をもっと知りたい!





とっておきの時間をサポートします
宿から体験までご要望に応じて、あなただけの滞在プランを手配させていただきます。
雪国観光舎(無休 9:00~18:00)
TEL 025-785-5353
カテゴリー別に探す
観光
公共・一般施設
交通施設


宿から体験までご要望に応じて、あなただけの滞在プランを手配させていただきます。
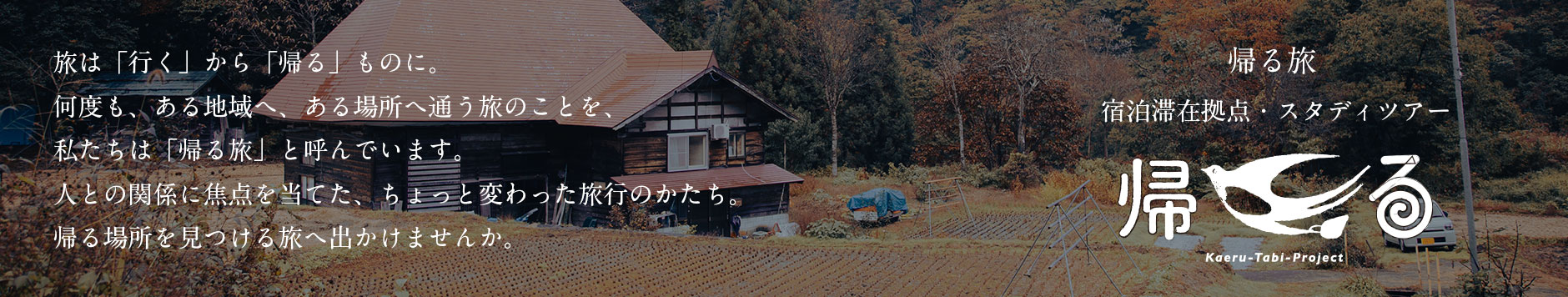



雪国文化をもっと知りたい!





宿から体験までご要望に応じて、あなただけの滞在プランを手配させていただきます。
雪国観光舎(無休 9:00~18:00)
観光
公共・一般施設
交通施設